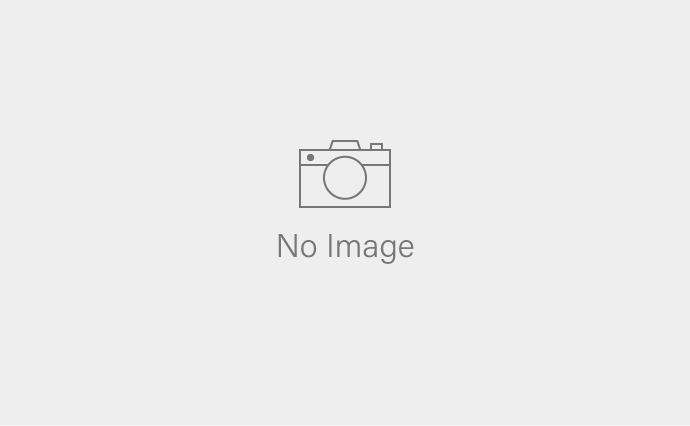階段を登るとたくさんの山が並んでいた。霞んで見える山の大きさは心に残るだろう。思いの詰まった、重いリュックを下ろし、大きく深呼吸をした。
空気は冷たくて、思い切り吸えば緑の味がした。ここに私しかいない。無風も珍しく、野鳥の声は景色いっぱいに響き渡っていた。私も返事をしたくなるほど、高揚していた。
リュックから飲み物を出し、コンビニで買ったおにぎりを食べた。なんとなく手作りの方が良かったように思える。野鳥へあげるご飯も用意していた。看板には「食べ物はあたえるな」とあるけれど、見えないふりをした。「食べ残しなくきれいに食べてくれるからいいでしょ」理由にもならないことを呟いた。
独り占めの時間は長くなかった。中年の男性がひとりで登ってきた。重そうなリュックを背負い、前傾姿勢で息が切れている。そんな重いものを持ってきて何をするつもりだろうと、黙って見てしまった。男性と目が会い挨拶を交わす。
「こんにちは、重そうな荷物ですね」大きな声が響いた。
「あー、これね、重かった」本当に重そうで、階段を登りきっているにもかかわらず、前傾姿勢のままだ。なんだかおもしろい。
「テントですか?」気になりだしたら止まらない。相手に嫌な思いをさせていようが、関係なく何でも聞いてしまうのは、悪いところだと、ひとりになるといつも思うことである。
「いや、ここはテントが張れないからね」地べたに座りこみ、荷物を下ろしたときリュックから液体が流れて、アスファルトの色が変わっていく。男性は急ぐように荷物を出して、急いで投げ捨てた。
私は呆気にとられ黙って見ることしかできなかった。
目の前に見える景色が霞んでいく。おいしい空気も、野鳥も遠くの山も、すべて見えなくなっていた。
「まさか、人が居るとは思わなかった」男性は下を向きながら、近づいてきた。何か雰囲気が気持ち悪いような、挨拶を交わした人じゃない。私は後ろに少し下がって逃げる覚悟をした。
「あれはさ、人間なんだよ、昨日腹が立ってバラバラにしてやったんだ、生意気なこと言うから」無表情で私を睨みつけた。殺される間違いなく落とされると確信した。
「私もそうだと思いました」得意げに顎を上げて言ってやった。男性は顔色を変えることなく黙った。
「私も捨てたばかりですからね」